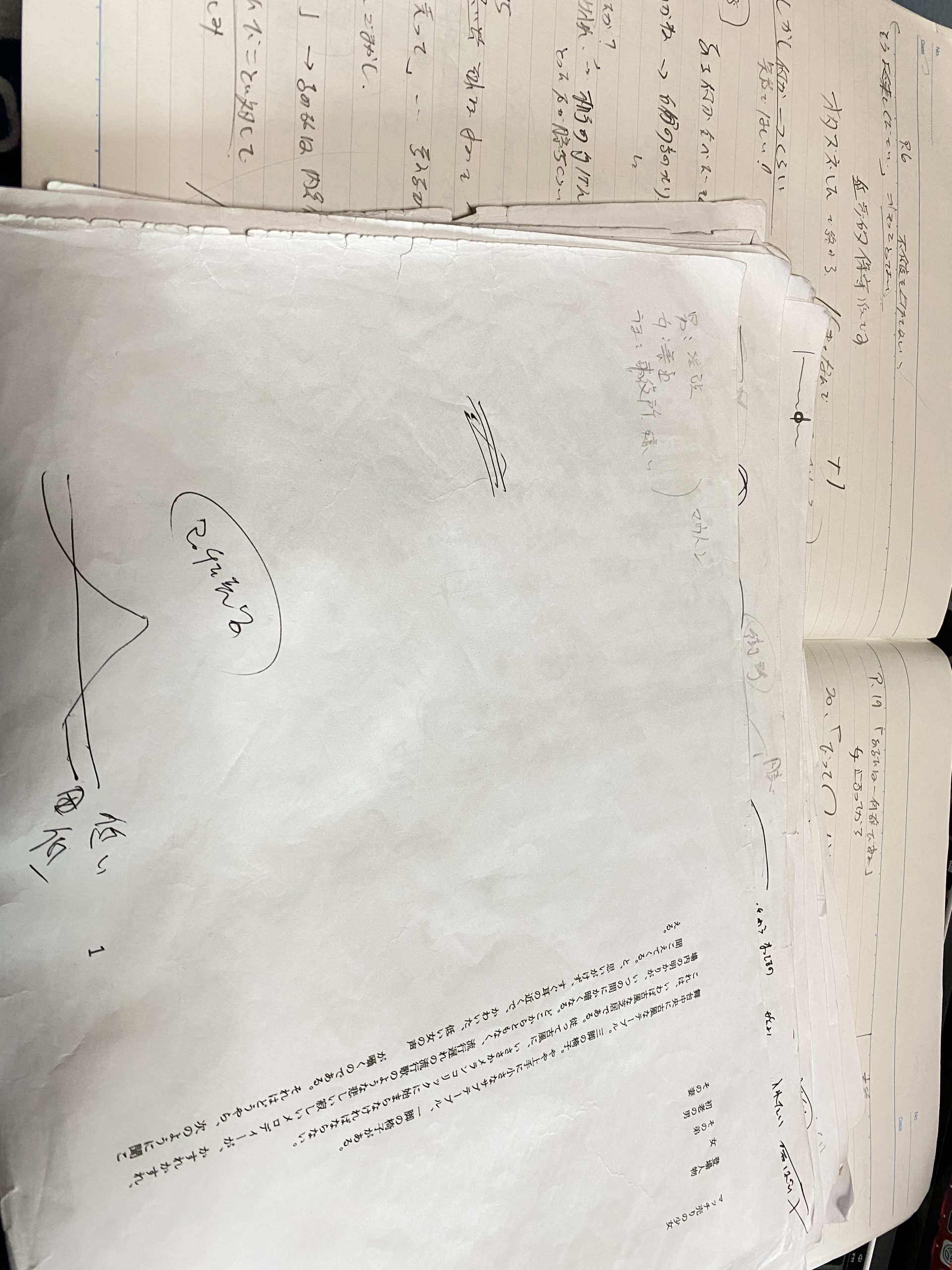最初読んだ時の感想
別役実マッチ売りの少女をどのように解釈しようとしているのか、考えをまとめてみたいと思う。
戯曲を初めて読んで持った感想としては、『笑えるサイコホラー』だと感じた。
一般的な夫婦の家庭に、記憶にない娘、記憶にない息子が出てくる。
それが「異常でありえない」にも関わらず、まともに対応してしまう夫婦。そのうちに、あり得ないが本当なのかもしれない疑念が読んでいるうちに湧いて出る。
あり得ないナンセンスさは、自らをマッチ売りの少女だと信じている女に対しても言える。
「ありえない」のに、物語の中で自らをマッチ売りの少女だと認識し、本当にマッチ売りの少女のように語っている。
そんな人間が思い込みの中で行動し、徐々にまともであった夫婦もそれに巻き込まれていく。例としては映画『黒い家』、『ファニーゲーム』のような不条理さを感じる。また、戯曲のブラックだが何故か笑えるようなイメージとしては、『未来世紀ブラジル』、常人を超えた思い込みで行動しているイメージとしては『何がジェーンに起こったか』が想像された。
と、いうような映画たちからわかるように、序盤から続く不条理に巻き込まれていく部分が印象に残った。
テーマは何?
しかし、ネット上の様々な解釈(戦後直後の日本に対する批判ー夫婦の卑しい過去を忘れたように生きる罪を、語らずに追求する女、弟)や、そもそもの不条理演劇の構成(テーマ性が根幹にあり、ストーリー演劇というよりは、むしろプロットとしての演劇)について調べていくうちに、ただホラーを描き出す不条理さを描くだけでは不条理演劇として正しくないのではないかと感じ始める。(正しい、正しくないの価値観については常に付き纏う問題となってしまったが)。
作品のテーマ性を考えるにあたって、まず印象に残った序盤のやり取りから考えることとした。
過剰に受け入れているように見える夫婦は、台詞から『可哀想な人は受け入れなければいけない』という価値観が存在していると分かった。
テーマ性がある作品とは、反対の性質を持つものが争うことで価値観の対立が確認できる。
対比としては考えた『ユキカタには根拠がなくてはならない』という夫婦と、根拠がない女、弟が存在している。
過剰に受け入れを是としている夫婦側のユキカタの根拠とはなんなのか。
それは所謂社会規範ではないだろうか。
社会を構成する一個人として、言語化されない当たり前を当たり前のように行動する。故に可哀想な人には優しくしないといけない当たり前な『社会規範』のために受け入れを行うのではないか。
序盤から続く受け入れ、物語を物語として成り立たせているものである、その社会規範こそ、『根拠がないユキカタ』なのではないかとふと思った。
女、弟による『マッチ売りの少女である+夫婦の娘である』という、思い込み。それを過剰に受け入れる善良にして模範的且つ無害な市民による『可哀想な人は受け入れなければならない』という社会規範。根拠のない思い込みで行動する女は受け入れられない存在としているが、根拠のない『社会規範』で行動する夫婦が受け入れられるのは何故なのか。当たり前は当たり前ではない。
社会規範がなぜ根拠たり得ないのか
なぜ、社会規範が根拠のないものだと判断したのかだが、そこには現代の普通がどうやって形成されているのかから判断した。
現代社会のあり方は、パノプティコン的である。誰もが他者の目を内面化し、演技している。突然大声を出すと、変な人にみられるから出さない。狭い道で相手を押しのけて通る際には、申し訳なさそうな仕草をする。また、それは他者にとって理解可能なものとして表出する必要がある。
申し訳ないと思っていても、申し訳なさそうな身体的な動き、息遣いをしていないと失礼だと解釈されてしまう。
つまり、私たちは社会の一員であることを証明するために、他者が望んでいるとされる行動を自らで理解できる形として表現し、全ての守るべき秩序、規範は、己の中にある他者の目線を通して形成されているということである。
コミュニケーションの場においても同様で、相手の話を理解している合図である相槌、相手の意見に合わせる同調や、「問い」に対して行う「返答」など。コミュニケーションにおいても、求められている姿がある。
逆に、例えば相手に合わせる「べき」であるときに、同意しない、相槌をしない。などをしてしまうと逸脱していると判断されてしまう。
コミュニケーションといったミクロな部分から演技は始まっているのである。
誠実な人であることを証明するためには、誠実そうにする演技をしなければならないようになってしまった。
そのように、相手の行為の意味を自己解釈によって成り立つ相互関係に真実は存在しない。守らなければならない社会規範も、守っているように見えればそれでよいだけで、カオスであることにかわりない。
だが、本人たちにとっては、過去行ってしまった逸脱した行為を自ら許容することはできず、ラベリング理論同様、自分自身ではどうしようもないレベルで、社会規範、共同体の一部としての認識は刷り込まれてしまっている。
そんな不条理なレベルで存在している「今」が劇中にはあるのだと思う。
コミュニケーションの相互理解についてのナンセンスさについても触れておきたい。以前こんなことを書いた。
パンフレットより
「行為の相互理解」により、一見秩序だって見えるという話を先ほどしたが、そもそものコミュニケーションの言語によるイメージ共有の難しさについても書きたいと思います。
各個々人によって言葉の解釈・定義は違い、自分の背景や体験から出る同じ音で共有をします。
会話とは相互コミュニケーションの中で、後天的に音に意味をつけていく行為です。
言語学にシニフィエとシニフィアンという言葉があります。シニフィエとは「意味」で、シニフィアンとは「音」です。
僕ら個人個人の関係性においての会話のやりとりは、意味として不確実性を持つ音の繋がりを用いて行われます。
発する側は自分の中のシニフィエを音を媒介して発し、受け手はそれを自らの中のシニフィエに合うように変換し受け取ります。
僕たちが他者とコミュニケーションをする時には、必ず自分の価値観やイメージを通して変換されたものを受け取る流れがあるということです。
その変換作業が入る時点で解釈というものが入ってしまい、相手と相互理解はできません。
同じ音、同じ動きでも、個人個人によって捉えられる意味は異なります。そんな曖昧なものに頼っているにも関わらず、お互いに相手を理解したと考えるのです。不思議です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結局どこまでいっても、自分の解釈でしか人間は行動できず、相手とわかりあうことはない。
そして共同体を構成しているものすらも、自己解釈の上に出来上がっている薄氷でしかない。
その存在を表したかっただけなのです。